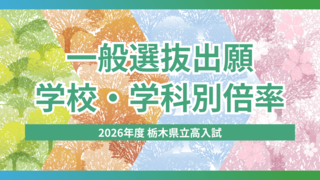【足利】今年開館30周年を迎えた市美術館で、豊富な所蔵品を紹介する「コレクション展2024」が開かれている。市ゆかりの画家大山魯牛(おおやまろぎゅう)(1902~95年)を中心に南画を取り上げた「パート1」(74点)と、元画商から寄贈された貴重な近現代美術を紹介する「パート2」(36点)の2部構成。戦後日本の前衛芸術をリードした中西夏之(なかにしなつゆき)のオブジェなども展示し、記念の年に相応した企画となった。6月30日まで。
南画は、中国の絵画に影響を受けて江戸後期に起こった画派の一つ。明治期に「時代遅れ」と批判され、人気が尻すぼみとなった。
今回の展示は、南画を大成した池大雅(いけのたいが)の小品で幕を開ける。旧足利藩士で多くの弟子を輩出した田崎草雲(たざきそううん)の作品は典型的な山水図に加え、「風神雷神図」で有名な琳派の影響を受けた金地のびょうぶも披露する。
草雲の孫弟子に当たる魯牛は、最後の南画家と呼ばれる。戦中戦後期にスランプとなり方向性を見失うが、抽象画との出合いに突破口を見いだした。
展示は草創期から晩年までの50点をそろえ、生涯を総覧できる内容。混迷期に描いた厚塗りの日本画のほか、1960年代に南画と抽象画を調和させた作品も集めた。紆余(うよ)曲折を経て、大胆でおおらかな画風へと展開していく様子が理解できるようになっている。
「パート2」は、50年代から戦後を代表する作家の展覧会を数多く企画した画商浅川邦夫(あさがわくにお)さん(91)が寄贈した「浅川コレクション」(890点)から厳選した絵画や彫刻などを展示する。
卵型の樹脂に日常の物体を封入した中西作の「コンパクトオブジェ」や、作家など多分野で活躍した赤瀬川原平(あかせがわげんぺい)のコラージュなど、戦後の美術界を代表する作家の作品が並ぶ。
浅川さんは「日本の芸術が一番ロマンチックだった時代の作品ばかり。ぜひ感じてほしい」と呼びかけた。観覧料は一般710円、大学・高校生500円、中学生以下無料。休館日は月曜(29日、5月6日を除く)、30日、5月7日。
 ポストする
ポストする