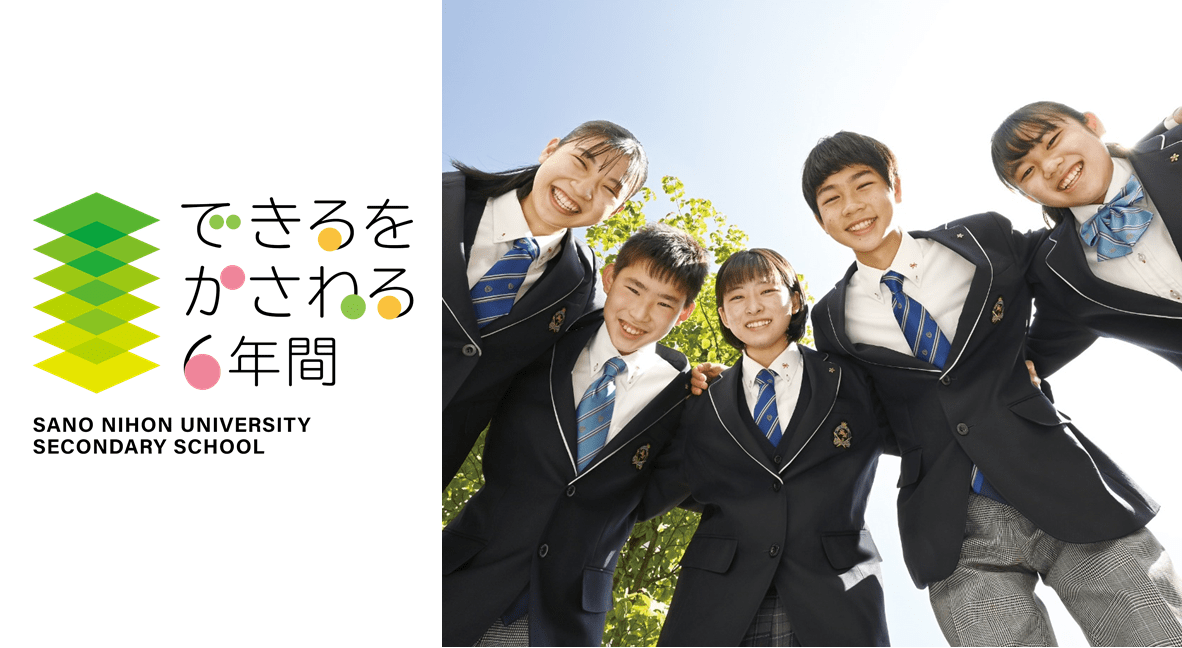中学、高校の6年間を一つの体系的な教育課程として学ぶ中等教育学校。佐野日本大学中等教育学校は県内初の中等教育学校として、2010年4月の開校から今年12年目を迎えた。どういった点が佐野日本大学中等教育学校の強み、魅力なのか。同校に話をうかがった。

中等教育学校は日本では1998年の学校教育法改正で設置が認められてからまだ20年余りと、比較的新しいスタイルの学校だ。2022年現在、全国で国公立、私立合わせ56校のみで、県内では佐野日本大学中等教育学校が唯一の存在であり、同校は中等教育学校としてすでに12年の積み重ねがある。なお、佐野日本大学高等学校とは同じ法人ではあるが別の学校である。
「『中学だからここまで』『この先は高校から』と分けず、6年間で合理的に学ぶプログラムを組んでいます」と話すのは同校入試室の大澤教諭。
同校では一般的な教科書に加え副教材として1年生から、数学ならば中高6年間を一つのスパンとして学ぶ「体系数学」(数研出版)を使用している。同様に英語ならば「Uncover(アンカバー)」(ケンブリッジ大学出版)、国語ならば「論理エンジン」(水王舎)など、アウトプット力や論理的思考力を養う教材を取り入れている。大澤教諭は「6年間を一つの単位として学ぶ中等教育学校、そして私立学校だからこそできるプログラムです」と力を込める。

ただ独自の教材使用を活かすには生徒の理解力も重要で、それを下支えするのが授業時間の多さだ。隔週で土曜日が授業となっており、教材をうまく生かして先へ進む仕組みになっている。様々な工夫によって高校の課程で学ぶ内容を、中学3年の10月から学び始めることができる。「本校では中学1年の段階で、すでに大学入試を視野に入れています」と大澤教諭。ただし、単に高いレベルの内容を学ぶのではなく、ユニークな副教材を活用することで「楽しく学ぶ」ことにも力点を置いているのが特長だ。
中等教育学校の場合、併設型中高一貫校と違い、高校から入学するケースがないため、6年間を同じ顔触れの生徒と学ぶことになる。中学と高校の間で一度リセットすることがないため、合理的に学習プログラムを組むことができる。同校では6年間のうちの前半3年間(前期課程)を地力を蓄える期間と位置づけ、後半3年間(後期課程)でさらに能力を開花させることを目指している。同校入試室長の細田晃良教諭は「本校の場合、入学時点では首都圏の難関私立中、有名私大系列中に比べ学力的には普通の生徒でも、6年生の時点では遜色ない水準まで伸びるケースも多いです。いわゆる『あと伸び』するということですね」と手応えをのぞかせる。医学部だけをみても、一昨年度はのべ14名合格(卒業生84名)、昨年度はのべ10名合格(卒業生59名)をはじめ、国公立大では、一昨年度は13名合格(一橋大、九州大、横浜国大、千葉大等)、昨年度も13名合格(北海道大、山形大、秋田大、福島大、群馬大等)を果たしたほか、早慶上理やGMARCH等、難関私大へ進む生徒もいる。日本大学系列校で、日大への進学が有利な点に加え、進学校としての顔もしっかり併せ持つ学校でもある。

同校では現在、各学年2クラス、6学年12クラスで約380人が学んでいる。6年間、同じメンバーということで育まれた絆も、生徒にとっては一生の宝物のようだ。細田教諭は「大規模校の場合、同じ学年でも、一度も話したことがない生徒もいるかと思います。本校ではそういったことはなく、お互いをよく知った者同士で6年間を過ごします。その分、卒業後の結びつきも強いのではないでしょうか。卒業後も、何人かで連れ立って学校に訪ねてくる卒業生も多いですね」と笑顔を見せる。
同校では生徒全員が個人用のノートパソコンを所持している。コロナウィルス蔓延による家庭学習時にも、ほぼリモートで授業を進めることができ、本来の進度に遅れることなく対面授業にもどることができた。現在ではさらに各教科でICTを活用した授業を進めていて、簡単な使用から始め、PC上の各クラスルームを使用しての伝達や、課題の配信・提出などが、前期課程でも普通に行われている。後期課程になると、個人のノートパソコンと電子黒板を使っての英語のプレゼンテーションなど、高度な使用にも発展している。細田教諭は、「現在でもコロナ関連の欠席者には普通にリモート授業が行われており、さらに対面授業のツールとして授業中には各生徒の机上にノートPCが置かれ、有効に活用されています。生徒のスキルも上がっており、学びを止めないこと以上の、より高度なICT機器の使用に取り組んでいきたい」と意欲を見せる。
同校のもう一つの魅力が、豊富な海外研修プログラムだ。現在はコロナの影響で中断しているが、高校2年相当となる5年生は例年、ホームステイも取り入れたイギリス研修旅行に参加する。このほか3~5年では希望者を対象としたオーストラリア、中国、東南アジアなどでのフィールドワークもある。6年間の幅でカリキュラムを組むからこそできる時間的なゆとりが、海外研修を充実させられる要因のひとつだ。細田教諭は「イギリス研修旅行を入学の決め手としていた生徒、保護者も多かったので、今の状況は大変残念。早い段階で再開できれば」と話す。
海外で学ぶ一番の目的は、多様性を身につけ、国際感覚を磨くこと。今はこちらから海外に行くことはできないが、同校に組織されているグローバル教育センターが中心となり、国際問題や環境問題をテーマにした大学教授・講師などの講演をオンラインで聴講する取り組みも行っている。
 ネイティブの英語教師が教える
ネイティブの英語教師が教える
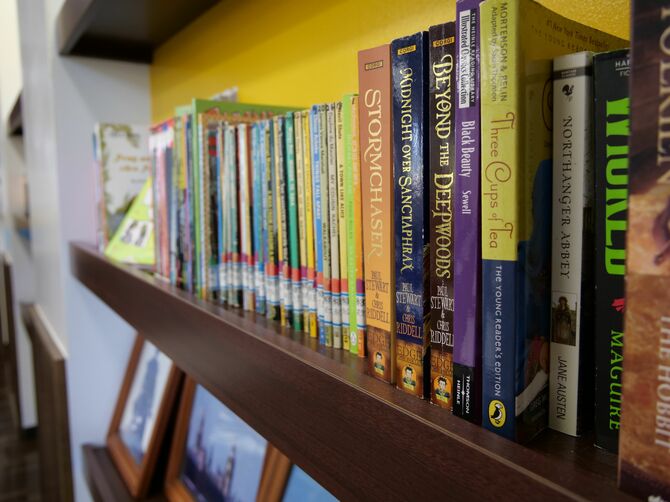 英語の教材が壁一面に並ぶ
英語の教材が壁一面に並ぶ
6年間を通じ高度な学力を育むことはもちろん、世界で活躍できるような能力と広い視野を備えた生徒を育てることを見据える佐野日本大学中等教育学校。グローバル社会において、その存在感はますます輝きを増していくだろう。
 ポストする
ポストする