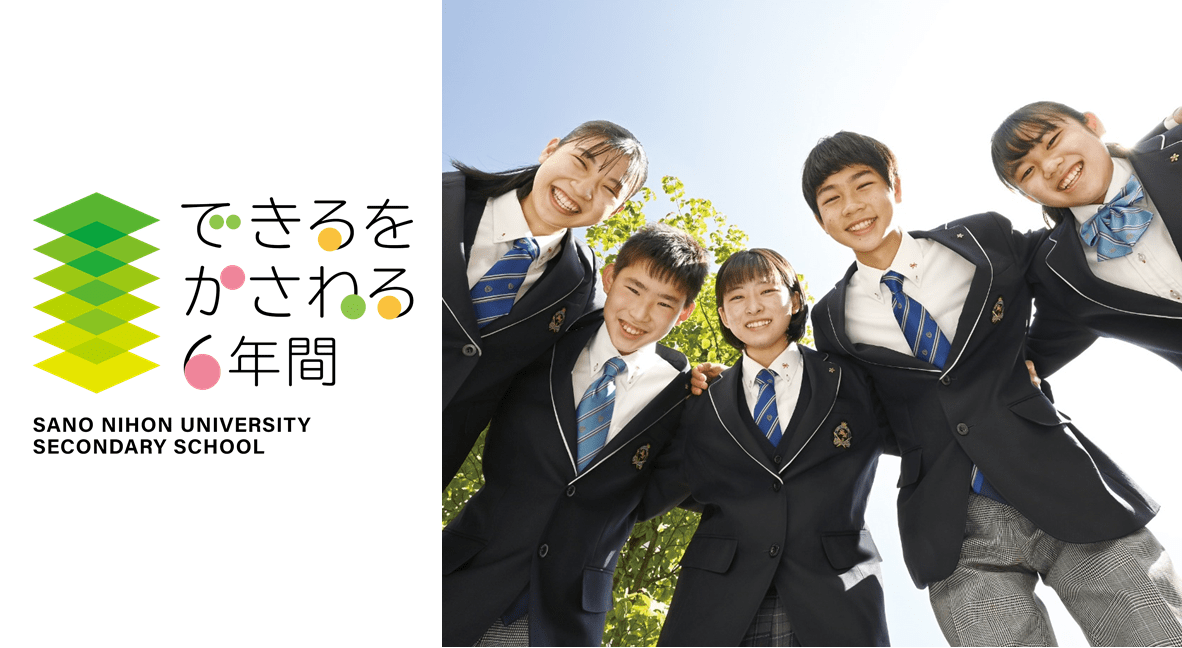今、教育界において学習テーマの主軸として扱われることの多い「グローバル教育」と「探究学習」。佐野日本大学中等教育学校では、これらの学習についても「日本大学の付属校であり、シームレスな6年間教育」だからこそできるアプローチで積極的に取り組んでいます。多様な社会で生き抜く力を身につけるための同校の教育を、具体的に伺いました。

「経験」という名の「引き出し」をつくるグローバル教育
「グローバル教育」という言葉は比較的よく耳にしますが、実はあまり明確な定義はありません。なんとなく「世界の国々のことを知る」というようなイメージが先行しているかもしれませんが、佐野日本大学中等教育学校では「この佐野にいながら、地域や自国のことを知り、そして世界を考える」ということをコンセプトとしています。
世界の中の日本、日本からの世界、という視点を軸に据え、「世界を考えるきっかけを与えるためのプログラム」を生徒たちに用意できるよう、学校全体で取り組んでいます。
「やみくもに『地球規模』のことを知るのではなく、世界の何かに接したとき、しっかりと感じて考えることができる思考力・判断力・表現力を身につけるために、『経験という名の引き出し』を可能な限り多くつくることに主眼を置いています」と語ってくれたのは、同校でグローバル教育を牽引している丹野先生。
今回はグローバル教育の事例として、
①イギリス研修旅行や、その他海外との交流プログラム
②日大提携校ならではのプロフェッショナルトーク
③「3.11を語り継ぐ旅」
という活動 の3つのケースを教えていただきました。
① 佐野日本大学中等教育学校では5年生時(一般の高2)に学年全体で「イギリス研修旅行」に行きます。これは単なる「海外修学旅行」ではありません。1年生時から積み重ねてきたアウトプット重視の独自の学習方法の集大成の場でもありますが、現地の提携校での学習やホームステイを通して現地の生活も体験します。
その他、マレーシアやオーストラリア、中国、ニュージーランド、ハンガリーなどとも提携し、定期的かつ安全なフィールドワークとして継続性のある経験の機会も用意。現地で体験して満足するだけでなく、それを日々の学習にも落とし込み、行き来して関係を作り出すことができます。
② 同校では、一般でいう中学生・高校生にあたる時から、大学の授業を経験できるのも特徴。総合大学である日本大学の付属校であることを活かして、「プロフェッショナルトーク」と称したまさにそれぞれの分野のプロフェッショナルの講義を受けることで、視野をぐっと広める機会を設けています。
例えば、理工学部の海洋建築学の教授による津波に対応する建築の授業、国際関係学部によるカースト制度の今を知る授業。知ると少なからずショックを受けることもあるけれど、普通に生きているだけでは触れることのない社会の課題をプロフェッショナルから直接学ぶことは、生徒に考えるきっかけを与えてくれます。
③ 「3.11を語り継ぐ旅」は「教えてもらう」研修旅行ではなく、生徒自身が「感じ取る」探究活動です。年に一度実際に東北を訪れて震災を経験された方々と様々な形で触れあうのはもちろん、日常に戻ってからも常に現地に思いを馳せる。なかでも「アイリンブループロジェクト」(※)への参画は、学校の花壇で東北から株分けされた花を育てる活動を通して震災の風化を防止すると共に、災害公営住宅にお伺いして被災地の「いま」に寄り添う活動となっています。 このチーム顧問の菅沼先生はおっしゃいました。
「東北の方から『出逢う喜び』を頂き『生きるエネルギー』をその背中に感じながら、生徒たちは楽しんで活動しています。共に活動する仲間との絆、東北の方々との交流を通して感じる喜び、現地の同世代の方々とつながる楽しみなどを得ながら、日々いきいきと活動しています。すべての企画は生徒主体で作っており、命の大切さを感じながら、自分たちでできることを考えて行動していく。彼らが大人になったとき、自分が身につけた力を『誰かのために』使える人間になってもらえたら…それが顧問としての願いです」。※「アイリンブループロジェクト」について
日本を知り、世界を知る。体験し、考える。佐野日本大学付属高校の「グローバル教育」の一部をお聞かせいただきましたが、それらは他では経験することのできない、同校ならではのプログラムでした。
「グローバル教育の狙いをシンプルに言えば、『ショックを与える』ということです。12歳から18歳の自分の小さな世界では知るよしもないことを、当校がさまざまな経験の機会を与えることで、たくさん知って、学ぶきっかけにしてほしい。そう思っています」(丹野先生)。
「答えのない問い」を見つけることから始まる「探究学習」
「総合的な学習(探究)の時間」という学習要項を文部科学省が打ち出し、まさにそのやり方を各学校で模索している今。小学校から高校まで、これを「探究学習」として取り組んでいます。
インターネットで検索すれば答えが出てくるようなことではなく、答えのない問いを見つけ、その解決に向けて情報を集めたり分析したりし、周囲と協力してその答えを求める学習活動が「探究学習」。佐野日本大学中等教育学校では、シームレスな6年であることを活かし、「1年生から4年生までのチームでの探究」と「5・6年での個人での探究」に段階を分けて取り組んでいます。

特に今年から始めた特徴としては、1年生から4年生で縦割りのチームを作り、探究に取り組む学習。チームで相談し、「答えが出ていないけれど追求したいテーマ」を見つけ設定するところからスタートしています。大人では考えつかないような実に中高生らしい研究テーマをそれぞれ掲げており、1年生は1年生らしい視点で上級生をはっとさせたり、4年生はチームをまとめる役割を担うことで成長したりする様子がすでにみられているそうです。
また、ここでも日本大学の付属校であるメリットを最大限に活用。それぞれのチームをテーマに合った学部と連携させ、探究のなかで浮かびあがってきた疑問や問題をその学部の教授に質問したり、プレゼンをするときにはその資料の作り方を教授に教えていただいたりすることを予定しています。
もともと「なにかのテーマについて探究すること」が大学での学習スタイルなので、この探究学習をサポートしてもらうには最高の関係といえます。
「普段の授業は正しい答えが存在し、正解を答えたい、というマインドのなかで学習をしているけれど、探究学習は『答えのないことすらも楽しむくらいのマインドを育てる』ということにもつながると思っています。例えば面接で質問を受けたときに、模範解答にとらわれず、『私はこう思います』とか『まだわからないけれど、こうなったらいいなと思います』というようなことを自信をもって話せるような人間になってもらいたい。通常の授業では私たちも正解を教えなきゃいけないけれど、この探究学習では生徒たちの発想に驚かされるし、なにを言われても「それもありえるかもしれないね」と言えることに新鮮さを感じているところです(笑)」と楽しそうに話してくださったのは、探究学習を担当している大橋先生。
先に出たグローバル教育も、「縦割り×高大連携」でスタートした探究学習も、すべては多様化が進む社会でしなやかに楽しく生きていくための力を身につける教育。中学生・高校生にあたる6年をこの佐野日本大学中等教育学校で学ぶことで、他では得られない広く深い体験をするチャンスを次々と与えられ、それを通して固定観念にとらわれない豊かな発想力をもった人間に育つことができることは間違いないようです。
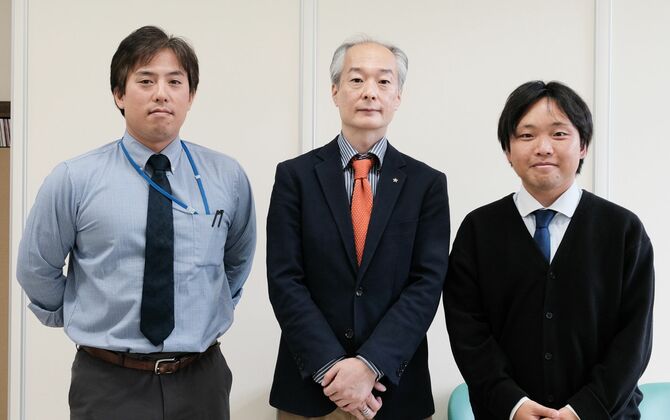
今回の学習内容を伺うに際し、数名の先生方にお話を伺いましたが、最後にこんな話が出ました。 「私たちが校長先生からいつも言われていることは、『生徒が明日も学校に来たいと思うようにしてくれ!』ということなんですよ!」
校長先生のこの言葉に代表されるように、一人ひとりの先生の熱量、生徒たちへひとつでも多く良い経験を与えたいという思いが伝わってきて、学校全体が同じ方向へ向かって進んでいる一体感を感じることができました。
前回も話したとおり、中等教育学校への入学を検討できるのは、小学6年生まで。佐野日本大学中等教育学校のこれらの教育に興味を少しでも持ったなら、ぜひとも一度オープンキャンパスに参加することをおすすめします。この限られたチャンスを逃さないよう、ご家族で検討してみてください。
 ポストする
ポストする