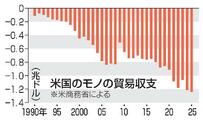違和感を抱いたことは、なかった。生まれ育った足尾のはげ山は、物心がつく前からの景色だったから。
煙害-。製錬所から出た亜硫酸ガスは、はげ山の理由の一つとされる。足尾銅山の元鉱員、浅見幸雄(あさみゆきお)さん(90)は、大人になるにつれ実情を知った。
思えば、ひどいものだった。
その煙は風と共に流れてきた。辺りに立ち込め、家の戸は開けられなかった。
「黄色い煙だった」。臭いも脳裏に染みついているが、「表現のしようがない」。思い返し顔をしかめて言葉を探すが、納得のいく表現は見つからない。
煙を見なくなったのは、1955(昭和30)年に坑内で働き始めた直後だった。蒸気のような白い物は出ていたが、臭くない。あまりの違いに驚いた。
抜本的な排煙対策が取られたのは56年。この年、経済白書は「もはや戦後ではない」とうたった。銅山はその17年後、閉山した。
浅見さんの長女、児玉美子(こだまよしこ)さん(62)にとっても、はげ山の記憶は鮮明だ。
友達と岩の斜面を登ったこともあった。8歳の頃、「危ないから」と言ったのに、ついてきた4歳下の弟が滑り落ちた。斜面の途中で柵のような物に引っかかって、助かった。
肝を冷やした場所は、製錬所近く。今残る煙突と比べると、それより高い位置のように見える。当時と異なるのは、周囲に木々が目立つこと。
国、県などによる治山事業は排煙対策が講じられた56年の後、本格的に展開された。女性たちが草木を根付かせる植生盤を担いで山を登ったり、ヘリを導入したりした時代もあった。96年に発足したNPO法人「足尾に緑を育てる会」は現在、官民協働で緑化活動を続けている。
帰省するたび、緑が増える。はげ山の頃を知る県外出身の夫も認めている。このごろは紅葉も楽しめる。
ただ世間のイメージは変わらない。「足尾銅山といえば鉱毒」。言われれば、いい気持ちはしない。「銅山で働く人がいた。大変な仕事だったんだ」との思いが募る。防じんマスクを着けた父、それを毎日洗う母を見てきたからだ。
「ここにも草木一本なかった。今は雑草だらけだけど」。自宅の居間から庭に目を向け、浅見さんがほほ笑んだ。「緑豊かな方がいい。気持ちがいいから」。あの頃と様変わりした景色がさらに広がり、子々孫々にわたり続くことを願っている。

 ポストする
ポストする