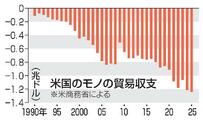「疲れなんて感じないわ。心が躍るの」
那須塩原市の自宅から6月上旬、日光市足尾地域西部の小滝地区を訪れた作家三浦佐久子(みうらさくこ)さん(93)の足取りは軽かった。
足尾訪問は約1年ぶり。最盛期は1万人以上が暮らし、今は建物跡の石垣が往時をしのばせる同地区。周りの山々を若葉が彩る様子に三浦さんは目を細めた。
1973(昭和48)年2月の足尾銅山閉山から間もない頃、40代で「ヤマ」と呼ばれた銅山の町に魅了され半世紀。足尾に立つたび胸中に湧く感慨は、初めて訪れた時から変わらない。
◇ ◇
紅葉の時季、友人に誘われたのが最初の足尾訪問だった。小滝の鮮やかな紅葉と、北部の荒涼としたはげ山。美しさと凄惨(せいさん)さの同居する情景が頭から離れなくなった。
一つの興味も芽吹いた。
「銅山一色だった町には、どんな人が暮らすのか」
鉱泥を使った「足尾焼」に地域振興の活路を見いだそうとした陶工、社宅の長屋や共同風呂で濃密な人間関係を築く老人-。閉山後、人が減り続ける足尾で生き生きと暮らす人々を訪ね歩いた。「壺中(こちゅう)の天地を求めて」と題して88(同63)年、書籍にした。自宅があった都内から片道2時間半をかけて通い詰めた。

翌年に写真家や俳人など、足尾にひかれた同志十数人と「足尾を語る会」を立ち上げた。地域を歩いて歴史や文化を掘り起こし、会報として発信した。住民を巻き込んだイベントも開いた。会報創刊号のあとがきには、こうつづられている。
「真実を求めてやまぬ目、声が集まり、恋うる足尾の未来を造る大河になることを切に願う」
◇ ◇
一時は約80人まで増えた語る会だが、高齢化が進み2019年に活動を終えた。だが、会員は今も足尾へ目を向け続けている。群馬県太田市の坂本寛明(さかもとひろあき)さん(51)はその1人だ。
「あれだけの鉱山をつくった人々の努力の姿勢にひかれてきた」
鉱毒被害と結びつけられがちな銅山の姿だけでなく、日本の近代化に貢献した側面に注目する。鉄道、発電所、公害防除の取り組み-。銅山の発展とともに培われた技術などを考察し、冊子にまとめてきた。今もたびたび足尾を訪れる。
足尾を愛する人たちが残した書籍や冊子。三浦さんはそれら記録の存在意義を信じている。
「活字として残れば誰かの目に留まる。そのときに1人でも2人でも、心に響けばいい」

 ポストする
ポストする