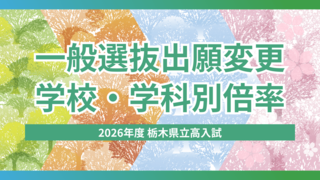今回は足利の人々に「大日(だいにち)さま」として親しまれている鑁阿寺にやって来ました。本堂は700年以上の歴史があるそうです。

鑁阿寺は1196年、鎌倉幕府を開いた源頼朝(みなもとのよりとも)の義理の兄弟だった源姓足利(みなもとせいあしかが)氏の2代目・足利義兼(あしかがよしかね)が邸宅の中に持仏堂(じぶつどう)(信仰する仏像などを安置させるための建物や部屋)を建て、大日如来(だいにちにょらい)を祭ったことが始まりとされています。
現在の本堂は1299年、室町幕府の初代将軍足利尊氏(あしかがたかうじ)の父・貞氏(さだうじ)が再建したもので、中国から伝わってきた当時最新の建築様式「禅宗様(ぜんしゅうよう)」がいち早く取り入れられています。
禅宗様の特徴は、「詰組(つめぐみ)」と屋根の反りです。当時の建物は屋根の重さを支えるために、柱の上に組物(くみもの)と呼ばれる部材が付いています。禅宗様の建物には柱と柱の間にも飾りの組物が取り付けてあり、軒下をより立体的に見せています。また、建物をより大きく見せるために反りの強い屋根になっています。

2009~10年に行われた屋根のふき替えに合わせて、本堂に使われている木材が伐採された年代を推定する科学的調査が行われました。その結果、本堂が建築されたのは鎌倉時代後期と分かり、これまでの説が裏付けられました。調査や文献をきっかけに、13年、県内の建造物で61年ぶりに国宝に指定されました。
このほか境内の鐘楼(しょうろう)と一切経堂(いっさいきょうどう)が国重文、楼門(ろうもん)や多宝塔(たほうとう)などの建造物が県指定有形文化財になっており、彫刻や文書も合わせると多数の文化財がそろっています。足利市文化課の高橋伴幸(たかはしともゆき)さん(47)は「“何があっても寺を守る”という人々の強い思いがあったからこそ、多くの文化財が残っているのではないでしょうか」と話しています。
今も残る“城”の面影
もともと足利氏の館だった鑁阿寺は「鎌倉時代の城」とも位置づけられ、歴史上の出来事と関わりがある跡地として国史跡に指定されています。

境内の周りを水堀(みずぼり)で囲い、掘った際に出た土を盛り上げて土塁(どるい)を築くなど、中世の武士の居館(きょかん)の面影を現代に伝えています。日本城郭(じょうかく)協会が選ぶ「日本100名城」に本県で唯一選ばれており、休日になると全国各地のお城ファンや歴史ファンが集まってきます。
また毎年節分には、鎧(よろい)を身にまとった市民らがまちなかを練り歩く伝統行事「鎧年越(よろいとしこし)」が行われます。これは足利泰氏(やすうじ)が、一族の結束などを見せつけるため500騎の武者を集めた出来事にならったものです。足利氏の力強さを感じますね。(武藤久美)
【どっとこ記者の感想】
足利の人々にとって、鑁阿寺は七五三や初詣(はつもうで)、この時季はお花見スポットとしても親しまれているんだって。今では市民の憩(いこ)いの場だけど、もともとは足利氏のおうちだったんだね。国宝や国重文をはじめ、たくさんの文化財があることにもびっくりしたよ。
【メモ】
足利市家富町2220▽開門時間 午前9時~午後4時▽(問)同寺0284・41・2627。詳しくは公式ホームページへ。
全文1520文字
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

 ポストする
ポストする