下野新聞は栃木県の地元紙として、宇都宮美術館の開館前から、同館の作品収集などの開館準備の様子を広く紹介してきました。また、1997年の開館以降も、その展覧会情報をいち早く紙面で取り上げ続けています。
今回、同館で開催されている、開館25周年記念 全館コレクション展「これらの時間についての夢」展は、「時間」をテーマとしています。そこで、12月1日から15日まで、毎日1回ずつ、このページ内で、本紙の宇都宮美術館の記事を再度掲載し、同館の歩みを振り返ります。
これ夢展 担当学芸員の一言
市政顧問(館長予定者)として、宇都宮美術館、そして、コレクションの礎を作った高見堅志郎氏のインタビュー記事です。
下記は1995年2月27日に掲載された記事です。
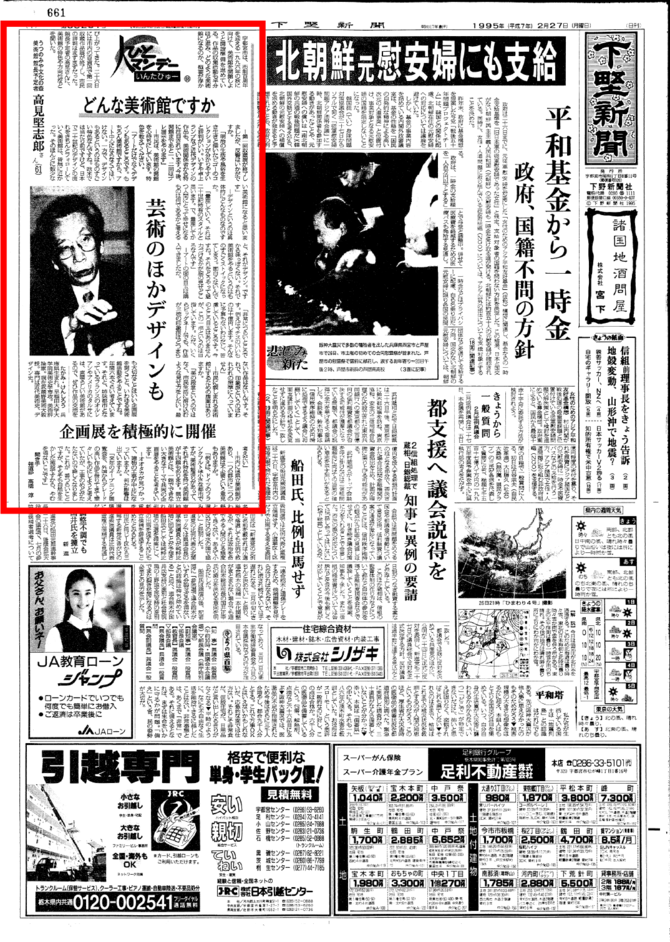
宇都宮市は、市制百周年を迎える一九九六年の秋に向けて、美術館を開館しようと開設準備を進めている。作品の収集活動も半分ほど進み、どのような美術館になるのか、概要が浮かび上がってきた。二十六日には市内の百貨店で第一回収蔵作品展が終了し、市民の評判はまずまずだった。館長予定者の高見さんに、美術館の特色や方向性などを聞いた。
‐第一回収蔵展が終了しましたが、反響はいかがですか。
「明治の生活や風俗を生き生きと描いたビゴーのコレクションが分かりやすいと評判がいい。いすや卓上ランプなど近代デザインの作品も、美術関係者から特に注目されています。今後、開館まであと一、二回はプレ展示をやります」
‐市民は、美術館の開館を心待ちにしています。特色を教えてください。
「アートだけでなくデザインもあるところです。もちろん美術館ですから、アート中心にならなくてはいけない。一方で、デザインもあるというのはものすごい特色なんですね。欧米では当たり前ですけど、日本で二十世紀のデザインの流れをきちんとフォローしていく美術館は、皆無に近かった。そのほんとに数少ない美術館になると思います」
‐デザインというのは具体的にどんなものなのですか。
「量産していく、それは二十世紀持有のスタイルと思います。で、量産してかつ人間にとって幸せになるものは何であるかと考えると、それがデザイン。ですから味っぽくない。それで美術館をやるというのはものすごくストイックになってしまう。面白くないんですね。それをどうやって魅力づけるかが腕の見せどころなんです」
‐アートの面の目玉は購入できましたか。
「非常につらいところです。例えばマチスのいいものは十億円します。そんなに予算もないわけだし、苦慮しているところです。今のところ目玉はありませんが、この一点というのは目指しています。ただ、いくらビッグネームでも、作品が三流の印象派ほどつまらない作品はないんです。それで、印象派というのはわれわれの照準に人つていません」
‐市民に親しまれる美術館にするための腹案はありますか。
「美の殿堂というのではなく、市民生活に溶け込むような見せ方をしたい。最も大切なことはいい企画展を開くこと、いわゆる美術館活動をやることですね。年間六本ぐらい考えています。それと、姉妹都市となっているフランスのオルレアンやアメリカのタルサには、素晴らしい美術館があるので、ぜひ作品の交流を考えたい」
‐市内には県立美術館があり、一つの都市に二つの美術館は不必要という意見もありますが。
「例えぱ、ドイツのフランクフルトは小さな都市ですが、美術館通りがあって、それぞれ特色を持つ美術館が十四館もあります。県立美術館とは、一館でできない大きなテーマで共同の企画展をやることも考えています」
‐オオタカが見つかって、建物の工事が中止になっていますが、何か影響は出ていますか。
「来年のオープニング展覧会を、外国からグレードの高い作品を借りてきて華々しいものにしようと考えていたが、工事のめどがたたないので難しくなりました。これが一番つらいことですが、そもそも自然を生かした施設ですから、やむを得ないことです」
 ポストする
ポストする













